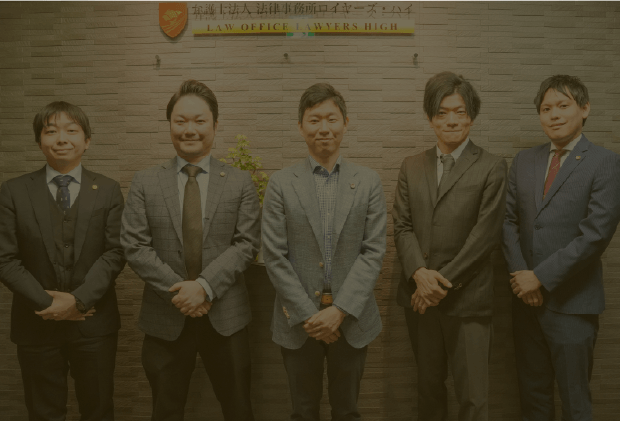法定労働時間を超えた場合に発生する割増賃金、または、所定労働時間(労働者が会社との間で契約した労働時間)を超えた場合に発生する賃金のことを残業代といいます。
法定労働時間は、原則として、1週間40時間、1日8時間を超えてはいけません。
①法定労働時間を延長して残業した場合、②休日に労働させた場合、③午後10時から午前5時までの間に深夜労働させた場合、通常の労働時間又は労働日の賃金に以下の割増率以上をかけた残業代を支払わなければなりません。
- ①時間外労働2割5分
- ②休日労働3割5分
- ③深夜労働2割5分
そして、使用者が残業、又は、休日労働を労働者に行わせる場合、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合と、かかる労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定(36協定)を交わし、これを行政官庁に届出なければなりません。
36協定には、これまで、法律上、残業時間の上限がありませんでした、近年の働き方改革によって、原則として、月45時間、年360時間の上限が定められました。
固定残業制とは
残業代は、月によって変動することから、使用者にとっては、人件費の予測が立てにくいところがあり、さらに、労働者が残業代欲しさに、本来なら法定労働時間内に終わらせられる仕事をあえて延長する、いわゆる「生活残業」の問題もあります。
そこで、これらを改善する方法として、使用者が、労働者の現実の残業時間の有無、時間数に関係なく、一定時間数の残業代を毎月定額で支給するという方法が、固定残業代制です。
種類
固定残業代の支配方法には以下の2つがあります。
・組み込み型
基本給に残業代を組み込んで支給する
・手当型
残業代の支払いに代えて定額の手当てを支給する
裁判例
では、この固定残業代制を採用するにあたってどのようなことに注意しなければならないでしょうか?2つの裁判例を紹介します。
〈組み込み型の裁判例〉
テックジャパン事件(最一小判S63.7.14労判523号6頁)
(事案)
基本給41万円、月間総労働時間が180時間を超えた時間については、1時間当たり一定額を別途支払い、月間総労働時間が140時間を満たない時間については、1時間当たり一定額を減額する旨の雇用契約を締結していた。
(判旨)
「月額41万円の基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同項の規定する残業の割増賃金に当たる部分とを判別することはできない」
(結論)
固定残業代制の有効性を否定
〈手当型の裁判例〉
日本ケミカル事件(最一小判H30.7.19労判1186号5頁)
(事案)
調剤薬局に薬剤師として勤務していた従業員に関して、雇用契約書では賃金月額に残業代金を含むとされ、給与明細書には「月額給与」「業務手当」が区分され、採用条件確認書には「業務手当」とはみなし残業代であること、および、業務手当は時間外労働30時間分として支給する旨の説明がされ、また、「残業代は、みなし残業時間を超えた場合はこの限りではない」と記載されており、賃金規程にも業務手当を「残業代の代わりとして支給する」と記載されていた。そして、実際の時間外数(1カ月平均28時間)と手当額に大きな乖離はなかった。
(判旨)
「雇用契約に係る契約書等の記載のほか、具体的事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して」、当該手当が残業等の対価として認められるかにより、固定残業代としての有効性を判断すべきである。
(結論)有効性を肯定
固定残業代制の有効要件
紹介した2件の裁判例、さらにH29.7.31基発0731第7号「時間外労働等に対する割増賃金の解釈について」の通達も含めて考察すると、組込み型・手当型を問わず、有効と認められるには以下の3つの条件が必要と考えられます。
①明確区分性
通常の労働時間の賃金部分と、固定残業代の部分とが明確に区別できることが必要です。
実質上、基本給に残業代を含んでいるとしても、給料支払明細書に単に「基本給」としか記載されていない場合は、明確に区別されているとはいえません。
②対価性
通常の労働時間に対する賃金と区別された手当が、時間外労働の対価であると認められることが必要です。
そのためには、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則、賃金規程などにおいて、当該手当が残業代の名目で支給されることが記載され、明確に判断できることが前提です。具体的には、固定残業代の項目、その金額、時間数を明示する必要があります。
また、形式的には規定があっても、業務内容や労働時間からみて、その手当が残業代の趣旨と認められない場合には対価性は否定されます。例えば「営業はいろいろとお金を使うから」との業務内容への配慮から支払っていた営業手当は、残業の対価であるとは言えません(アクティリンク事件東京地判H24.6.29)。
③差額支払い合意
そして、実際の残業時間に基づいて法定どおり計算した残業代が固定残業代を上回っている場合は、その不足分を支払う必要があります。
さらに、固定残業代制を採用するにあたって、労働者ごとに個別に同意をもらわなければならないことはもとより、固定残業代制の導入にあたって、基本給の減額を行う場合は、それに伴う不利益について十分な説明をしたうえで、この場合も労働者ごとに個別の同意をもらうことが必要です。
注意点
残業代をあらかじめ固定することは必ずしも違法ではありませんが、使用者側にとってはメリットの多い制度であるものの、労働者にとっては歓迎すべき制度とは言い難いのは事実です。また、法整備もされておらず、会社自身が前もって違法・適法の線引きをするのは困難かと思われます。
そして、定めた定額残業代が無効とされた場合には、残業代は未払いと判断されます。結果、その定額残業代も基本給として扱われ、この基本給+定額残業代を基準とした割増賃金を、残業代として支払わなければなりません。さらに、未払い残業代全額を上限とする付加金支払いのリスクも忘れてはいけません。
固定残業代制の導入を考えている、あるいは、すでに導入しているが有効性が心配だという企業におかれましては、弁護士、社会保険労務士などの専門家に、制度内容の点検・吟味をしてもらうことをお勧めします。

 06-4394-7790
06-4394-7790 お問い合わせ
お問い合わせ