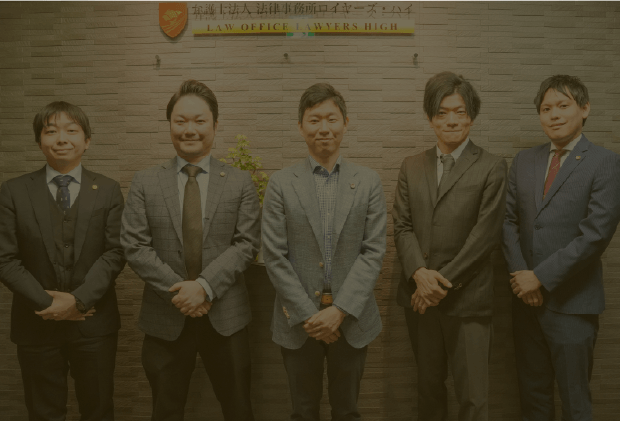日本の労働基準法では、「1日8時間、週40時間」という法定労働時間が決まっており、このラインを超えて働いた分は残業代支給の対象になります。ただし、実際に働いた時間(実労働時間)を明確に定義しにくい職業もあります。専門性が高い職業や、成果が重視される職業ですね。こういった職業は「裁量労働制」が採用されています。では、一般的な会社員が裁量労働制で働いたとき、残業代は請求できるのでしょうか。ここでは、裁量労働制と残業代の関係について解説します。
そもそも裁量労働制とは?
裁量労働制は、実際に働いた時間をカウントするのではなく、あらかじめ「働いたとみなす時間(みなし労働時間)」を決めておく制度です。また、裁量労働制は「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」に分類されます。具体的には次のとおりです。
裁量労働制が適用される業務
裁量労働制が適用される業務は、おもに2種類です。労働基準法では、第38条の3および第38条の4で規定されています。
○第38条の3「専門業務型裁量労働制」
デザイナーやコピーライター、システムコンサルタント、その他専門性の高い士業など専門性が高い職業が対象
○第38条の4「企画業務型裁量労働制」
企画、立案、調査及び分析の対象業務を行うにあたり、業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し、使用者から具体的な指示を受けない事務系労働者
簡単に言うと「ホワイトカラーのうち企画・調査に携わる者」
これら裁量労働制の対象となる職種では、原則として出退勤の時間を自分の裁量で決められるため、残業代という概念がありません。
例えば、みなし労働時間が1日7時間である場合、繁忙期で11時間働いたとしても、残業代は請求できません。言い換えれば「みなし労働時間が法定労働時間の範囲内」であれば、残業代を請求できないわけです。ただし、いくつかの例外があります。
裁量労働制でも残業代を請求できるケース
裁量労働制であっても残業代を請求できるケースは、次の3つです。
裁量労働制の条件を満たしていない(不当に適用されている)ケース
裁量労働制の対象業務は、前述した通り「専門性の高い職種」や「企画・調査を主な業務とする一部のホワイトカラー」です。しかし、あたかもこれらに該当するようにみせかけて、実際には他の業務を担当させているケースが少なくありません。
例えば、「専門業務型裁量労働制」の場合は、設計や分析に関わらないプログラマー、考案された図案をもとに製品を作る作業者などが典型例です。こういった職種は、上位者の指示に従うことが大半で、仕事の自由度が低いという特徴があります。にもかかわらず、裁量労働制の対象として残業代が支給されていないわけです。
「企画業務型裁量労働制」の場合も同様で、調査や分析、戦略立案以外の業務が大半を占めるにも関わらず、裁量労働制が採用されているケースがあります。このように、「労働の実態が裁量労働制の適用対象ではない職種」については、残業代の請求が可能です。
深夜や法定休日に働いているケース
裁量労働制であっても、深夜や法定休日の労働に対しては、残業代が支給されることになっています。つまり「夜22時~朝5時の間」と「労働基準法で定められた最低基準の休日」です。法定休日については、労働基準法の第35条に規定されています。
”第35条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。”
深夜の場合は1.25倍、法定休日の労働に関しては1.35倍の時給で請求可能です。
みなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超えているケース
裁量労働制で残業代が発生しないケースは、あくまでも「みなし労働時間が法定労働時間の範囲内にあるとき」です。つまり「みなし労働時間が1日あたり8時間以内」であることが条件です。みなし労働時間が8.5時間や9時間の場合は、超過分を残業代として請求できます。就業規則で「みなし労働時間≦8時間」となっているかを、しっかり確認してみてください。
残業代請求の交渉の相談は専門家へ
このように、裁量労働制においても、残業代が請求できる可能性は十分にあります。そもそも裁量労働制が適切に運用されていないこともありますから、少しでも疑問を感じたら専門家へ相談すべきです。残業代の請求においては、証拠集めや企業側との交渉が発生します。また、最終的に裁判で争う可能性も否定できません。労働者が会社と争うとなれば、疎外感や罪悪感に苛まれることも少なくないでしょう。
ひとりで企業と戦おうとせず、まずは労働問題に強い弁護士への相談を検討してみてください。

 06-4394-7790
06-4394-7790 お問い合わせ
お問い合わせ