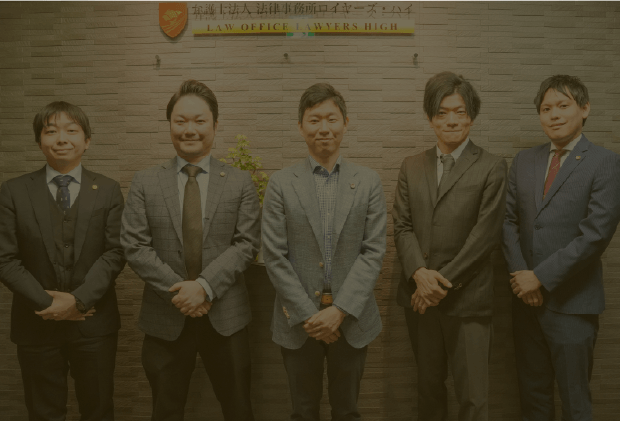サービス業及び接客業は飲食業、小売業、ホテル・旅館業、など多種多様にありますが、人々の日常生活にかかわるものが多く、その結果、土日休みなく営業が行われるため、比較的残業時間が長くなる傾向がある業種ともいえます。
労働基準法では、労働時間は1日8時間、1週間40時間までと定められており(常時10人未満の労働者を使用する場合は、1週間44時間まで可能(労働基準法施行規則25条の2))、これを超えると時間外労働として残業代が発生します。この「1日8時間、1週間40時間まで」という要件はそれぞれを満たす必要があります。すなわち、1日10時間労働した場合は、たとえ1週間40時間以内であっても、1日の超過時間分の2時間については残業代が発生することになります。
しかし、サービス業等では繁忙期と閑散期があり、繁忙期ではこれを守ることは難しく、他方、閑散期には労働時間の短縮さえ必要になる、ということは珍しくないでしょう。そのようなときに、これから説明する「変形労働時間制」を導入して、労働時間を月・年・週単位で調整することで、勤務時間が増加しても時間外労働とは扱われず、多額の残業代の発生を抑えることができます。
変形労働時間制
[変形労働時間制とは]
労働時間を月単位・年単位で調整することによって、繁忙期等により勤務時間が増加しても時間外労働としての取り扱いを不要とする労働時間制です。
簡単に言うと、定めた大きな時間単位で労働時間を把握し、それより小さな時間単位では制限しない、ということです。これにより、忙しいときは1日10時間、1週間で合計40時間働き、週休3日にするということが可能となり、労働者にとっては、メリハリをつけた働き方ができるというメリットがあります。会社にとっては、変形労働時間制の範囲内であれば残業代が発生しないことから、繁忙期・閑散期という波に合わせて残業代コストを削減するというメリットがあります。
種類としては、以下の3つがあります。
- ①1カ月単位の変形労働時間制
- ②1年単位の変形労働時間制
- ③1週間単位の変形労働時間制
実際に、多く用いられているのは①②です。以下、種類ごとに確認していきましょう。
[各種変形労働時間制]
①1カ月単位の変形労働時間制
これは、1カ月以内の一定期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内の範囲であれば、1日8時間、週40時間を超えていても時間外労働とはならないという制度です。
(要件)
この制度を採用するには、労働協定または就業規則等によりこの制度を採用する旨を定め、①労働日、労働時間の特定をすること、②変形期間の所定労働時間を法定労働時間内とすること、③変形期間の対象期間および起算日を明確に定めることを労働者に周知させることが必要です。
(残業代が発生する場合)
1日8時間を超えかつ所定労働時間を超えている場合、1日8時間を超えていないが1週間40時間を超えている場合、1日8時間、1週間40時間を超えないが月の法定労働時間を超えている場合、残業代が発生します。
②1年単位の変形労働時間制
これは、1カ月を超え1年以内の一定期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以下の範囲で、特定の日または特定の週で、1日8時間または1週間40時間を超えて労働させることができる制度です。
ただし、特例措置対象事業場の1週間44時間の労働時間に対しては使用できません。
(要件)
この制度を採用するには、労使協定によりこの制度を採用する旨を定め、①労働者の範囲、②対象期間、起算日、③対象期間における労働日と労働日ごとの労働時間、④特定期間、⑤労使協定の有効期間を定める必要があります。
(残業代が発生する場合)
1日8時間を超えかつ所定労働時間を超えている場合、1日8時間を超えていないが1週間40時間を超えかつ1週間所定労働時間を超えた場合、対象期間の法定労働時間総枠を超えている場合、残業代が発生します。
③1週間単位の変形労働時間制
常時30人未満の労働者を使用する小売業、旅館、料理店・飲食店において、1週間の労働時間が40時間の法定労働時間を超えない範囲で、1日10時間まで勤務を設定できる制度です。
1週間を単位に、業務の繁盛時、閑散時に応じて設定できます。
ただし、この制度も1カ月単位の変形労働時間制と同様に特例措置対象事業場の1週44時間の労働時間に対しては使用できません
(要件)
この制度を採用するためには、所定労働時間は、1日10時間以内、1週間40時間以内とすること、1週間の各日の始業及び就業の時刻と休日を、その始まる前までに労働者に書面で通知することが必要です。
(残業代が発生する場合)
1日8時間を超えかつ所定労働時間を超えている場合、1週間の法定労働時間40時間を超えている場合、残業代が発生します。
名ばかり店長
小売業、飲食業のチェーン店においては、正社員が店長とされ、あとはパートである場合が多く見られます。店長は、その名のもと、管理監督者として、労働時間、休憩、休日について適用除外とされる場合が多く見受けられます。
[労基法上の「管理監督者」とは]
労働基準法上の「労働時間」「休憩」「休日」についての適用が除外される管理監督者(労基法41条2号)とは、一般的には、部長、工場長等の労働条件の決定その他勤務管理について経営者と一体的な立場にある者をいうと理解されています。
そして、管理監督者として認定されるためには、①経営者と一体的な立場で仕事をしていること、②出社、退社、勤務時間について裁量があること、③賃金等について地位相応の待遇がされていることが必要です。
- ①については、一般の従業員と同様の業務に従事している、アルバイト・パート等の採用に関する責任と権限がない、勤務割表の作成の権限がないといった場合には、否定されます。
- ②に関しては、出勤予定表に従って勤務している、遅刻、早退等により減給の制裁がある、営業時間中は店舗に常駐しなければならないなど長時間労働を余儀なくされる場合等には、否定されます。
- ③に関しては、他の従業員との手当の差額が数万円であったり、実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算した賃金額において、アルバイト・パートより低い賃金である場合には、否定されます。
[コメント]
管理監督者に該当するかは、最終的にはケースバイケースで判断せざるを得ませんが、実際の裁判で管理監督者該当性が認められることは多くはありません。
管理監督者でないと判断されると、労働基準法上の「労働時間」の適用がされ、法定労働時間の範囲を超えれば、残業代を支払わなければなりません。かなり長時間労働を強いられている場合が多いので、結果的には、高額の未払残業代の支払いを命じられます。そこに裁判所によって未払い賃料と同額の付加金を支払わせられるというリスクも加わります。
「管理監督者」とする場合の業務内容や待遇面を、今一度見直すことをお勧めします。

 06-4394-7790
06-4394-7790 お問い合わせ
お問い合わせ