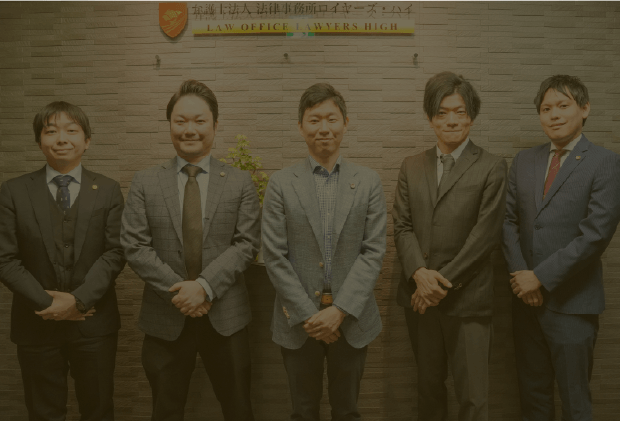法定労働時間を超えた場合に発生する割増賃金、または、所定労働時間(労働者が会社との間で契約した労働時間)を超えた場合に発生する賃金のことを残業代といいます。
法定労働時間は、原則として、1週間40時間、1日8時間を超えてはいけません。
①法定労働時間を延長して残業した場合、②休日に労働させた場合、③午後10時から午前5時までの間に深夜労働させた場合、通常の労働時間又は労働日の賃金に以下の割増率以上をかけた残業代を支払わなければなりません。
- ①時間外労働2割5分
- ②休日労働3割5分
- ③深夜労働2割5分
そして、使用者が残業、又は、休日労働を労働者に行わせる場合、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合と、かかる労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定(36協定)を交わし、これを行政官庁に届出なければなりません。
36協定には、これまで、法律上、残業時間の上限がありませんでした、近年の働き方改革によって、原則として、月45時間、年360時間の上限が定められました。
年俸制とは
賃金を1年単位で決定する仕組みを年俸制といいます。
年俸を採用する業種としては、IT業界で働くプログラマー、システムエンジニア、ディレクター、スポーツ選手、コンサルタント業務、医師などが挙げられます。
年棒制であるからといって、賃金の支払いは1年に1回というわけではありません。賞与がない場合は、年俸を12か月で除した月単位の賃金を労働者に支払う必要があります。
年俸制のメリット
使用者にとっては、従業員の仕事の成果、能力を1年単位で評価して翌年の給与に反映することで、給与の増減を柔軟に行うことができ、その一方で、年間の人件費の変動を抑えることができます。
また、労働者にとっては、向こう1年、意に反して給与を減額されないというメリットがあります。
年俸制における残業代
一般に「年俸制には残業代が出ない」とのイメージがありますが、年棒制は給与額の定め方に関する仕組みに過ぎず、残業時間に関する労基法上のルールは当然及びます。そこで、年俸制の残業代に関してよく問題となるケースについて説明します。
①明確区分性
年俸制を採用して、それに残業代も含めることはできますが、固定残業代制の場合(高知県観光事件最判H6.6.13)と同様に、通常の賃金部分と残業代部分を明確に区別できるようにしておく必要があります。
医療法人社団Y会事件(最判H29.7.7)
(事案)
私立病院に勤務する年俸1700万円の外科医が未払い残業代の支払いを求めた事件です。この1700万円の年棒には本給・諸手当・賞与が含まれ、これとは別に「医師時間外勤務給与規程」に従って残業に対する給与が支払われていました。雇用契約では、この規程に定められた一部の残業についてのみ割増賃金の対象となるとされ、それ以外の通常業務の延長とみなされる時間外勤務については割増賃金の対象外であり、年俸に含めるという合意がされていました。
(判旨)
裁判所は、当事者において合意がされていたものの、このうち残業等に対する割増賃金に当たる部分は明らかにされていなかった点を指摘し、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分を判別することはできないとして、給与規程には定められていない時間帯における残業代が年棒に含めて支払われたとすることはできないと判断しました。
このように職業や賃金の額に関係なく、そして年俸制においても、通常の賃金部分と残業代部分を明確に区別できる必要があります。
②労基法37条による規制
通常賃金部分と残業代部分が明確に区別できるとしても、割増賃金の支払いを確実に使用者に支払わせることによって超過労働を制限するという労基法37条の趣旨は尊重されなければなりません。
ワークスアプリケーションズ事件(平成26年8月20日東京地裁判決)
(内容)
会社は元従業員に対して、年俸額の約14分の1を基本給として、年俸額から計算式により算出される金額を営業手当という名称で、50時間分の残業代を支払っていました。
この事件では、残業代部分が通常賃金部分と明確に区別はできるものでした。しかし、賃金規程において、その算定方法が、月平均所定労働時間を168時間と設定して定められていたところ、実際は、165.33時間であったため、所定労働時間を168時間として計算すると基礎賃金は下がることになります。その結果、営業手当は、労基法37条、労規則19条1項に定める計算方法により算出される残業代の額を必ず下回るかたちになりました。そこで、裁判所は、このような条件を定めた賃金規程は無効であり、営業手当をもって残業代の一部支払いがあったとは認められないと判断しました。
この裁判例からもわかるように、年俸制では、割増賃金の支払いが確実に支払われるよう、とくに月平均所定労働時間の設定に細心の注意が必要です。
他の制度との併用・代用
年俸制が採用される従業員は、通常、給与額の水準が高い場合が想定されるので、残業代が発生することになった場合、会社にとって当初予定していた年俸額を大幅に超えることになってしまいます。賃金負担を軽減したい使用者としては、できるだけ残業をさせないよう配慮が必要です。
その一方で、ワークスアプリケーションズ事件からもわかるように、年俸制を採用する従業員の労働時間を正確に想定するのは、非常に困難な作業です。
事業場外みなし労働制・専門型労働裁量制
そこで、年俸制を採用した上で、労働時間管理に伴う負担を軽減する方策としては、事業場外みなし労働制、または、専門型労働裁量制との併用が考えられます。これらの制度は、労働時間について労働者の裁量が大きいという点で、年俸制と近似しており、併用しやすいと思われます。
高度プロフェッショナル制度
さらに年俸制に代わるものとして、働き方改革で認められた高度プロフェッショナル制度の利用を検討すべきです。
高度プロフェッショナル制度とは、職務範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とするなどの業務に従事する場合に、時間外・休日・深夜の割増賃金などの規定の適用が除外されます。労働時間は賃金に反映されず、成果によって賃金が決まり、労働時間も自分で決められるというものです。
もっとも、要件として、一部の業種(研究開発、アナリスト、コンサルタント、金融商品のディーラー、金融業品の開発)につく労働者のうち、年収1075万円以上の者に限定されています。

 06-4394-7790
06-4394-7790 お問い合わせ
お問い合わせ