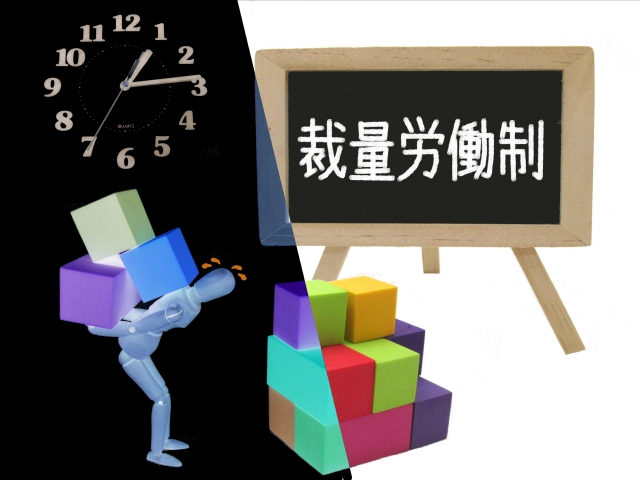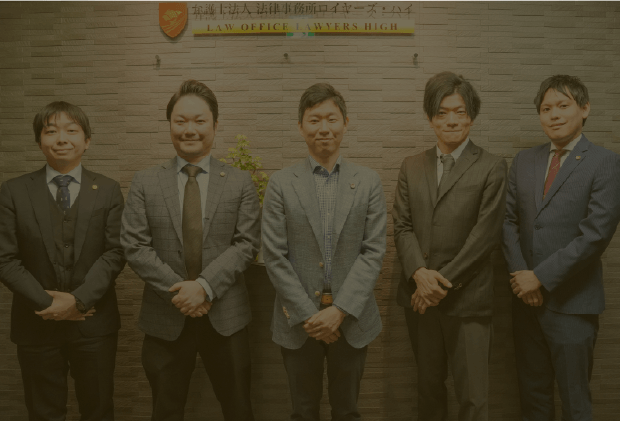法定労働時間を超えた場合に発生する割増賃金、または、所定労働時間(労働者が会社との間で契約した労働時間)を超えた場合に発生する賃金のことを残業代といいます。
法定労働時間は、原則として、1週間40時間、1日8時間を超えてはいけません。
①法定労働時間を延長して残業した場合、②休日に労働させた場合、③午後10時から午前5時までの間に深夜労働させた場合、通常の労働時間又は労働日の賃金に以下の割増率以上をかけた残業代を支払わなければなりません。
- ①時間外労働2割5分
- ②休日労働3割5分
- ③深夜労働2割5分
そして、使用者が残業、又は、休日労働を労働者に行わせる場合、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合と、かかる労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定(36協定)を交わし、これを行政官庁に届出なければなりません。
36協定には、これまで、法律上、残業時間の上限がありませんでした、近年の働き方改革によって、原則として、月45時間、年360時間の上限が定められました。
【専門業務型裁量労働制(労基法38条の3)】
労働時間は、実労働時間によって算定するのが原則です。
しかし、専門的な業務ではその性質上、その遂行を労働者の裁量に委ねる必要があるため、時間配分の決定等に関して、使用者が具体的に指示することが困難な場合があります。
そこで、このような専門的業務について、以下の内容を労使協定で定めた場合には、みなし労働時間を働いたとされることにしました。具体的には、みなし時間が8時間の場合、実際には10時間働いたとしても、8時間だけ働いたものとみなされます。このように、実労働時間に応じた残業代が発生しないことになります。
- 労使協定の締結とその内容
- ①弁護士業務、税理士業務、情報処理システムの分析又は設計業務など、厚生労働省令(労基則24条の2の2第2項)で定められた業務であること(19業務)
- ②みなし労働時間数
- ③対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと
- ④対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置
- ⑤対処業務に従事する労働者からの苦情処理に関する措置
- ⑥労使協定の有効期間(労働協約の場合は不要)
- ⑦労働者ごとの健康福祉措置・苦情処理措置の記録を、⑥の有効期間満了後3年間保存すること
- 「エーディーディー事件」(大阪高判H24.7.27)
- 「レガシィ事件」(東京高判H26.2.27)
- 注意点
労使協定の締結とその内容
専門業務型裁量労働制が適用されるには、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)を締結することが必要です。また、この労使協定書を所管の労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
この労使協定には以下の事項を定める必要があります。
①弁護士業務、税理士業務、情報処理システムの分析又は設計業務など、厚生労働省令(労基則24条の2の2第2項)で定められた業務であること(19業務)
平成5年改正前の労基法では、専門業務型裁量労働制の対象業務は例示列挙方式であったものが、同年の改正により、省令によって限定列挙する方式に変更されました。裁量労働制が、割増賃金の支払いを不要とするもので、賃金面で労働者の不利益になる可能性があるため、その対象業務をできる限り明確化すべきという趣旨です。
②みなし労働時間数
みなし労働時間数自体が法定労働時間を超える場合は、超えた分について、残業代が必要となります。
③対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと
この点がよく問題となります。裁判例を後述します。
④対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置
裁量労働制が労働時間の長短に関係なく、仕事の成果が重視される業務を対象とすることから労働者の働き過ぎにつながりかねず、健康についての相談室を設置するなどの措置が必要となります。
⑤対処業務に従事する労働者からの苦情処理に関する措置
⑥労使協定の有効期間(労働協約の場合は不要)
⑦労働者ごとの健康福祉措置・苦情処理措置の記録を、⑥の有効期間満了後3年間保存すること
(裁判例)
上記③の『対象業務』該当性が争われた著名な判例を2件、紹介します。
「エーディーディー事件」(大阪高判H24.7.27)
コンピューターシステム会社「エーディーディー」でシステムエンジニアとして勤務していた元従業員が、実際は裁量外の労働をしていたとして残業代を請求した事件です。
会社は8時間のみなし労働時間制を採用していました。正社員として勤務していた原告は、主業務のシステムエンジニア以外にもプログラミングや営業活動にも従事していました。その業務実態は、タイトな納期が設定され、ノルマを課される、さらには、本来支給されるべき休日手当や深夜手当が全く支給されないというものでした。
裁判所は、「裁量労働制が許容されるのは、技術者にとって、どこから手をつけ、どのように進行させるのかにつき裁量性が認められるから」であるとした上で、タイトな納期の設定やノルマを課していたこと、営業活動にまで従事させていた等の事実を踏まえて、拘束性の強い具体的な業務指示があったとして、専門業務型裁量労働制の対象業務には該当しないと判断して、結果、原告の請求が認められました。
「レガシィ事件」(東京高判H26.2.27)
税理士法人及び総合コンサルティング業務を目的とする株式会社に正社員として雇用されていた元税理士補助スタッフが、在職中の時間外労働に対する割増賃金等の支払いを求めた事件です。
原告となった元スタッフは、公認会計士試験を合格しているものの税理士名簿への登録はされていませんでした。その業務内容は、税務相談の対応や申告書類の作成、土地の簡易評価の資料作成も行っており、実質上税理士の業務と同等のものでした。
裁判所は、平成5年の労基法改正により、裁量労働制の対象業務が、それまでの例示列挙方式から限定列挙方式に変更された趣旨について丁寧に言及し、対象業務はできる限り明確化すべきと述べました。その上で、「『税理士の業務』とは税理法3条所定の税理士となる資格を有し、同法18条所定の税理士名簿への登録を受けた者を主体とする業務をいう」と判示しています。そして、「その業務を行う手段や時間配分の決定などについて使用者が具体的な指示をすることが困難か否かという観点から実質的に解釈することになれば『税理士の業務』概念の外延は曖昧となり、対象業務の明確性が損なわれてしまうから、相当でない」と述べて、拡大解釈を否定しています。結果、原告の業務は専門業務型裁量労働制の対象業務にあたらないとして、原告の請求を認めました。
注意点
この専門業務型裁量労働制を採用すれば、使用者側にとっては、労働時間が管理しやすい、また、労働したとみなされた労働時間が法定労働時間内である限り、実労働時間が法定労働時間を超えていたとしても、残業代の支払いをしなくてもよくなり、残業代を抑えることができます。他方、労働者側にとっても、専門業務は裁量に委ねられて働き方の自由度が高まり、定められた時間は労働したものとすることができます。適切に運用されれば、双方にとってメリットの高い制度です。
もっとも、この制度をするにあたって、以下の点について、注意が必要です。
- 1.休日労働の賃金・割増賃金及び深夜労働の割増賃金については、このみなし労働時間制の適用がなく、これらの割増賃金を支払う必要があります。
- 2.対象業務の該当性がないということになれば、みなし時間労働の適用がなく、通常の労働時間とされて、法定労働時間を超えれば、その分、残業代を支払う必要があります。
- 3.ご紹介した判例からもわかるように、裁量労働制を採用したからといって、即、残業代の支払いを免れるというものではありません。対象業務該当性や業務の裁量保持については、実際の業務内容や遂行態様、専門業務以外の従事状況、福祉措置等の職場環境といったものも含めて総合的に判断されます。
専門業務型裁量労働制を採用するにあたっては、法律や各種行政通達に従い、対応策を十分に検討することが必要です。

 06-4394-7790
06-4394-7790 お問い合わせ
お問い合わせ