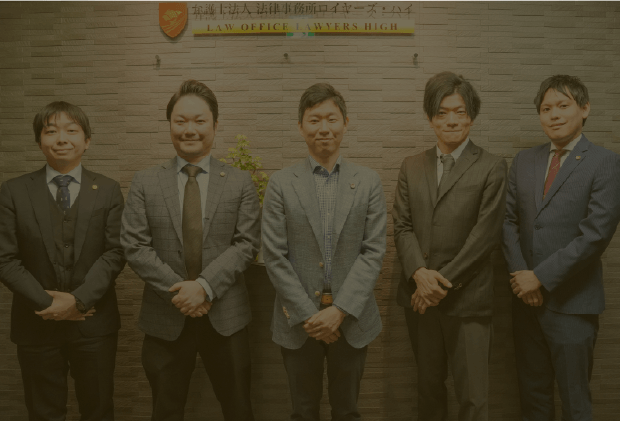法定労働時間を超えた場合に発生する割増賃金、または、所定労働時間(労働者が会社との間で契約した労働時間)を超えた場合に発生する賃金のことを残業代といいます。
法定労働時間は、原則として、1週間40時間、1日8時間を超えてはいけません。
①法定労働時間を延長して残業した場合、②休日に労働させた場合、③午後10時から午前5時までの間に深夜労働させた場合、通常の労働時間又は労働日の賃金に以下の割増率以上をかけた残業代を支払わなければなりません。
- ①時間外労働2割5分
- ②休日労働3割5分
- ③深夜労働2割5分
そして、使用者が残業、又は、休日労働を労働者に行わせる場合、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合と、かかる労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定(36協定)を交わし、これを行政官庁に届出なければなりません。
36協定には、これまで、法律上、残業時間の上限がありませんでした、近年の働き方改革によって、原則として、月45時間、年360時間の上限が定められました。
歩合制とは
売上高や生産高などの成果に対する一定割合で賃金額が決められる制度をいいます。
一般には、不動産販売の営業職、自動車販売の営業職、生命保険の外交員、タクシー及びトラックの運転手などの業種において広く採用されています。
成果を上げれば上げるだけ労働者にとって収入も増えるので、モチベーションが上がります。他方、会社にとっても、会社が儲かった時だけ多くの給料を払えばいいことから、経営の合理化を図ることができます。
歩合給の仕組み
では、売上が極端に低くなった場合は、それに応じて、歩合給も極端に低くてもいいのかといえば、そうはいきません。労基法27条は、使用者は労働者に対して、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない旨を規定しています。
一般的には、固定給と併せて通常賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるのが妥当と考えられています。
また、歩合給においては賃金の変動が非常に大きいことから、この保障給だけでなく、都道府県ごとの最低賃金を下回らないように確認しておく必要があります。この最低賃金を下回るかどうかについては、歩合給を除いた固定給のみで判定するのではなく、歩合給も含めたうえで、最低賃金を判定することになります。
完全歩合制とのちがい
実際に出した成果にのみ報酬を支払うという完全歩合制は、雇用された労働者ではなく、独立した個人事業主との業務委託という形式をとれば可能になります。この場合は、当然労基法の適用外となり、労働時間の計算や残業代支払い義務等の規制から外れます。
しかし、「労働者」に該当するかは、契約の体裁や名称ではなく、実態により判断されることに注意が必要です。
- 仕事内容や遂行方法について具体的指示命令を行っている
- 指定の場所・時間で勤務することを求めている
- 仕事の依頼や指示を断ることを認めていない
- 代理によって仕事を行うことを認めていない
- 他社での業務に従事することを認めていない
- 営業経費や備品を支給している
- 同様の業務に従事している自社社員と同程度の報酬水準である
これらの事情が認められる場合には、自社の「労働者」として労基法の規制が及ぶことになります。
歩合制の残業代
タイムカードや出勤簿等で労働時間を把握し、労基法に従って給与を計算しなければならないのは、歩合制であっても同様です。
すなわち、法定労働時間を超えて労働した場合には、残業代が支払われなくてはなりません。すなわち、労働者は、「1日8時間」もしくは「週40時間」を超えて労働した場合には、その超過時間分について、保障給を時給に換算した残業代と、残業代に上乗せした割増賃金を受け取ることができます。
〈賃金規程で歩合給から残業代を差し引くことの有効性〉
会社としては、従業員に対する賃金負担の増大を抑えたい、労働効率性も優先したいとの考えから、歩合制を導入することが多いかと思われます。そこで、基本給と歩合給で賃金を構成する場合、実際の労働時間外労働については労基法37条の割増賃金等を支払うものとしつつ、歩合給の部分については、業績に基づき算出された金額から割増賃金を控除した金額として、あらかじめ賃金規程等で規定することは認められるのでしょうか?
国際自動車事件最判H29.2.28
(事案)
タクシー会社「国際自動車」の運転手14人が、歩合給から残業代を控除する賃金規程は無効であるとして、未払い賃金等の支払いを求めた事件です。
(特色)
- 国際自動車では、賃金が①基本給、②残業代、③歩合給で構成されていたところ、③の歩合給が、売上高によって算出される金額から②の金額を控除されたものとして算出することが規定されていた。
- その結果、売上高が同じであれば、残業をしてもしなくても賃金の総額が同じ金額となるものあった。
(判旨)
最高裁は、労基法37条が労働契約における通常の労働時間の賃金をどのように定めるかについて規定していないことを理由に、労働契約において、歩合給から割増賃金に相当する額を控除したものを通常の労働時間の賃金とする旨の規定は、同条の趣旨に反し公序良俗に反するとはいえないと判断しました。
その上で、労基法37条の割増賃金を支払ったと認められるかどうかは、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とに判別できるかどうかで判断すると、従来からの判例の判断に沿ったものになりました。
この明確区分性を改めて検討すべきとして、高等裁判所に審理を差し戻しました。
〈差戻後の東京高裁判決H30.2.15〉
差し戻し審では、明確に判別できるとして、労基法37条の趣旨に反さず、公序良俗に反し無効ではないと判断しました。
その上で、裁判所は、歩合制は成果主義に基づく賃金であるから、労働の成果に応じて金額が変動することを内容としており、労働成果が同じである場合、労働効率性を評価に取り入れて、労働時間の長短によって歩合給の金額に差が生ずるようにその算定過程で調整を図ることは不合理なことではないとも述べています。
まとめ
使用者にとって、理想的な賃金額の決定は、労働者が生み出す価値の大きさに応じてその額が決まるというものではないでしょうか。歩合給は、売上げ、利益、製造個数など出来高に応じた支払いを内容としており、使用者にとっては望ましい構造といえます。
もっとも、「歩合給」という体裁で、従業員は長時間労働を余儀され、会社は残業代の支払いから免れるというからくりは、決して許されるものではありません。現に国際自動車事件と同様な歩合給を規定していた事件において、労基法37条の趣旨に反し、規定は無効であると判断されています(札幌地判H23.7.25)。その理由として、時間外及び深夜の労働を行ったときに、場合によっては歩合給が減額することすらあり、労基法37条の趣旨を潜脱するとしています。
今後の判例の動向に留意しつつ、使用者側におきましては、適正かつ誠実な給与支払いを心掛けたいものです。

 06-4394-7790
06-4394-7790 お問い合わせ
お問い合わせ