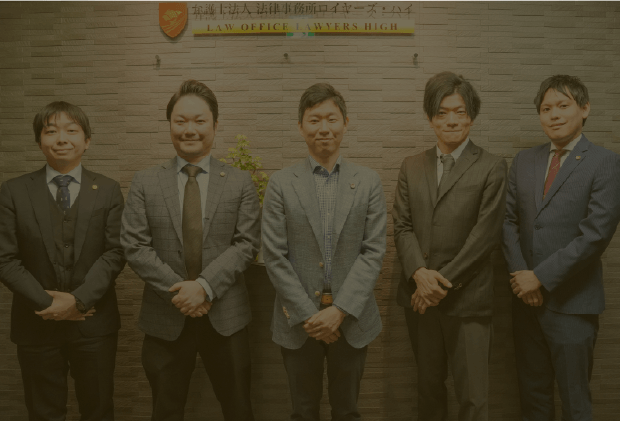もし残業代が支払われていない場合には、未払い残業代の請求が可能です。このとき、本体の金額にペナルティーを上乗せして請求できることをご存じでしょうか。いわゆる「付加金」や「遅延損害金」と呼ばれるものです。ここでは、未払い残業代における付加金と遅延損害金について解説します。
付加金と遅延損害金
まず、遅延損害金と付加金について、簡単に解説します。
遅延損害金
残業代を含む未払い賃金には、支払が遅れたことによる損害として「遅延損害金」が付きます。任意交渉や労働審判などでは、和解の前提として遅延損害金が省略されることも少なくありません。しかし、あくまでも「譲歩」の一環という位置付けで省略されるのです。一方、裁判による判決では、遅延損害金を含んだ金額が提示されます。遅延損害金の特徴は、在職中か退職後かによって利率が変動することです。
- ・雇い主が営利法人、もしくは個人で在職中の場合…年率6%
- ・雇い主が非営利法人の場合…年率5%
- ・退職日以降…年率14.6%
厳密にいえば、遅延損害金は在職中にのみ請求できるもので、退職後の部分については「遅延利息」と呼ばれます。退職前の遅延損害金は、商法514条や民法404条を根拠として請求されますが、退職後の遅延利息は「賃金の支払の確保等に関する法律」が根拠となっています。そのため、これだけ利率に差があるわけです。
付加金
一方付加金は、雇い主に対するペナルティーの側面が強く、未払い残業代そのものや遅延損害金に上乗せされる金額です。付加金は裁判所の判決以外では加算されません。(労働審判でも付加金は通常加算されません。)また、裁判所の判決全てで付加金が加算されるわけでもありません。つまり、裁判所の裁量によって「場合によっては付加金が追加されることもある」という程度のものです。よほど悪質な場合をのぞいて、付加金が加算されるケースは稀という認識を持っておいたほうが無難でしょう。
ちなみに付加金は、残業代の本体金額と同等なものを請求できます。これは労働基準法114条が根拠です。
“労働基準法第114条 付加金の支払
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。”
つまり未払いの残業代が50万円であれば、付加金も50万円で請求可能ということです。また、付加金が請求できるのは、次の項目で未払いがあったときです。
- ・解雇予告手当
- ・使用者の責に帰すべき休業の場合の休業手当
- ・時間外労働に対する割増賃金(残業代です)
- ・法定休日労働に対する割増賃金
- ・深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)
- ・有給休暇中の賃金
さらに付加金自体にも判決確定の翌日から年利5%の遅延損害金が加算されるため、会社側にとっては非常に大きな負担になるわけです。
付加金が加算されるケースとは?
付加金が加算されるのは、特に悪質と判断された場合のみです。では、どのような事例が悪性と判断されるのかを整理してみましょう。
悪質と判断され付加金が加算されるケースの例
- ・残業代の証拠(勤務記録など)を適切に開示しない、もしくは隠蔽した
- ・和解や譲歩に協力する姿勢がない
- ・残業代未払いの程度や労働者側の負担が甚大である
付加金が加算される条件は法律で決まっておらず、裁判所の裁量に任されています。したがって、実際に加算されるかどうかはともかく、請求時に付加金を含めておく、という対応が求められます。
付加金請求を見据えた対応を
このように残業代請求では、遅延損害金と付加金を含めた計画が必要です。特に付加金については、実際に受け取ることは無くても「本体部分の支払いに応じなければ、訴訟で付加金を請求する」という態度を示すことによって、相手方をけん制する効果もあります。前述のとおり、付加金は未払いの残業代を2倍、3倍と膨れ上がらせる可能性がありますからね。企業にとっては脅威なのです。ただし、遅延損害金や付加金の請求には裁判が必要ですから、まず弁護士へ相談し、実際に請求できる金額はいくらなのかを確認してみてください。場合によっては、想定してよりも大きな金額を請求できるかもしれません。

 06-4394-7790
06-4394-7790 お問い合わせ
お問い合わせ